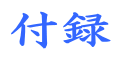 |
| 船着岩(ふなつきいわ)への探検 その1 |
| ◆このページで説明することを参考にした結果,起こった損害についていかなる保証・責任も負いませんので,あくまでも自己責任において行ってください. |
| 2013年6月8日作成 |
| 「船着岩(ふなつきいわ)」とは,岡山県岡山市南区彦崎にある稲荷山(標高154m)の東斜面にある大きな岩である.「立石(たていし)」とも言うらしい.山の下から見ても目立つ大きな岩で,かなり気になる存在である.木々が生い茂る斜面でも岩が顔をのぞかせていることから,岩の高さは7〜8mくらいあるのではないかと推察する. |
  稲荷山(瀬戸大橋線・植松駅の南側に位置し,瀬戸大橋線の蜂峰山トンネルが通っている) |
船着岩についてインターネットで調べてみると,熊野権現(熊野三山の祭神である神々)が海を渡って児島にやってきたとき,この岩に舟を繋いだから「船着岩」と呼ばれるようになったらしい.ただし,「灘崎町史」(昭和57年10月発行)のp.248には「彦崎貝塚の位置から考えて,この岩に舟が着くことはあり得ない」とのことである. 参考: 備前の古社を訪ねる(備前国内神名帳の研究)コラム202.舟着岩 ここで,彦崎33観音を紹介する.稲荷山がある彦崎には33観音があり,彦崎の各地に観音様が祭られている.灘崎公民館彦崎分館の駐車場に彦崎町内会案内図の看板があり,彦崎33観音の位置が大ざっぱな地図で示されているので参照してほしい. 彦崎にある熊山(標高240m)の山頂にある如意輪観音を1番として,稲荷山のふもとにある稲荷宮にある如意輪観音が27番である.なお,1番の如意輪観音を探しに熊山にも登ったので,後日,報告する. |
 →拡大 →拡大彦崎33観音の場所が示された彦崎町内会案内図 |
2013年3月26日,稲荷山を登り,船着岩まで行ってみることにした.ただ,稲荷山のふもとのどこから登ればよいか分からなかったので,とりあえず,稲荷山のふもとにある稲荷宮の27番観音へ行ってみることにした. 案内図の場所を頭に入れ,行ってみると,28番の聖観音を見つけた.その聖観音の横にはご丁寧に27番の如意輪観音への入口を示す看板が立っていた. |
 彦崎33観音 28番の聖観音 |
看板の通りに歩を進めていくと,畑があり,農作業をされている年配男性がおられた.その男性に観音様はどこか尋ねてみると,「この坂道をもう少し上がっていったら,鳥居があるからすぐに分かる」と言われた.さらに船着岩への道を尋ねてみたら,「昔は船着岩への1本道があったが,今はもう道はないだろう」とのこと.とりあえず,その1本道の入口を教えてもらえた. 男性にお礼を言って,稲荷宮に行ってみた.赤い鳥居があり,ほこらにはお菓子などがお供えされていた.そして看板付きで27番の如意輪観音もあった.赤い鳥居に「正一位稲荷大明神」と書かれているので,これが正式名称なのだろう.インターネットの地図には,稲荷山のふもとに「正一位稲荷大明神」と記されている. ここから船着岩へ行けないかと考えたが,稲荷宮の横にある斜面には木々がビッシリと生い茂り,人が山に入っていけるような所はなかった. |
  稲荷山のふもとにある稲荷宮と彦崎33観音 27番の如意輪観音 |
稲荷宮を後にし,坂道を下り,再び会った男性に挨拶して,船着岩への1本道の入口と言われる場所に向かった.下の地図に示すように馬場上公民館の方から赤線で示す上り坂(アスファルト舗装)がある.この坂道を上がっていくと,10体が並んだお地蔵様や墓地があるのだが,その途中で青色の矢印のように船着岩への道の入口がある.もちろん入口を示す看板はない. 下の写真では,入口を黄色の矢印で示す.写真右端がアスファルト舗装の上り坂である.この場所は,さすがに地元の人でないと分からないだろう.教えてくれた男性に感謝である. |
  稲荷山の東側の地図と船着岩への道の入口 |
入口から稲荷山に入りると,確かに1本道があった.しかし,20mほど進むとその道はなくなり,木々が立ち並び,落ち葉や枝で覆われた斜面がひたすら続く光景が広がるばかりである.斜面の傾斜はかなりきつく,木に捕まりながらではないと,登れないような斜面であった. あれだけ大きな船着岩だし,斜面での視界は,木々が多いとは言え,20m先くらいは見えたので,すぐに見つかるだろうと思っていた.しかし,大きな岩は全く見えず,道なき道を進みながら,稲荷山の中を彷徨うばかり.稲荷山の中には谷があったり,素人では登れない崖があったりと,船着岩を探すだけでもかなりの苦労であった. |
 稲荷山の斜面(カメラは水平にして撮影しました) |
稲荷山の斜面で岩を見つけ,「おっ」と思ったが,これはさすがに小さかった.探し回っていると自分が稲荷山のどのあたりにいるのか分からなくなったため,山頂を目指すことにした. |
 稲荷山の斜面で見つけた小さな岩 |
ひたすら斜面を這い上がり,ようやく到着.周囲を見て,一番高い所を撮影したのが,下の写真である.山頂では,岡山児島線(県道21号線)を走る車の音がやたらよく聞こえた.山頂には三角点があることを知っていたのだが,山頂と思われる場所から少し離れた所に杭(三角点?)があった. 参考: 岡山の山と三角点(稲荷山) そして山頂から,船着岩があるであろう方向に向かって下っていった. |
  稲荷山の山頂? 三角点? |
結局,1時間ほど,稲荷山の斜面を彷徨ったが,あの大きな船着岩を見つけることができなかった.悔いが残るも疲労感があるので,船着岩を諦め,斜面を下りていった.下りて稲荷山から出た場所は,レックタウン灘崎の住宅街であり,稲荷山に入った所とは少しずれていた.住宅街に隣接する山の斜面から人がいきなり出てきたら,見た人は驚くだろう. 稲荷山を改めて見ると,山頂が2つある.今回,辿り着いたのは下の写真で示す青矢印の山頂であり,標高154mの山頂は赤い矢印の方だった.次回の稲荷山登山では,船着岩を発見するとともに,本当の山頂に辿り着くことを心に誓うのであった. 2013年5月に2回目の稲荷山登山を行い,船着岩発見と稲荷山登頂を達成したので,後日,「船着岩への探検 その2」として報告する. |
 稲荷山の真の山頂(赤い矢印) 青い矢印は今回到達した場所 |