
直径40センチ×高さ40センチのドラム缶を
それぞれ15個注文しました。
どちらも1個あたり1000円+輸送料500円+消費税。
このドラム缶に、まず、さび止めを塗ります。
今度は黒の水性ペンキを塗ります。
30個全部塗るのにかなり時間を費やしました。
しかし、いくら丁寧に塗っても、
どうしても、色むらができます。
再び黒の水性ペンキで二度塗りしました。
今度は塗りやすく、
前日より早く作業が済みました。
クラレ(株)に勤務しているメンバーに、
要望書と一緒にお願いしたら、
2メートル×36メートルのロールを2本
無料で頂くことができました。
ありがとうございました。
直径40センチの円にあわせて型を作成。
いくつか試作品を作って、このサイズに決定。

床にしゃがんだままの作業で、持病の腰痛が発生。
この日は、整骨院に直行。
切り取りはいろんな人が手伝ってくれました。
左は5年生の女の子。
おしゃべりしながらも、はさみを一生懸命動かしてくれました。
この後、折り返しをつけてボンドを塗り、
ホッチキスで固定。
ポンチで穴を開け、ハトメをはめ込む。
ハトメは12ミリ20組で300円。
そこで、黒の布テープで補強してみました。
これで仕上げたのは5個。
というアドバイスを受け、残り25個はゴムで補強。
YKKの製品K-6426。
80メートル、3000円。
ただし、ゴムだと引っ張る際に止めてしまう心配があるので、
クラリーノとの接地面にはクリームを塗りました。
さて、引っ張って太鼓にした後は、
どちらがいいんでしょうか。
20メートルのロープを試してみましたが、
実際にはもっと長いロープの方が、
無駄がなくて、経済的です。
そこで、きちんと編み込んだ、
最高級の「新幹線印組ロープ」を購入しました。
8ミリ×200メートルを2巻。
10ミリ×200メートルを1巻。(原価25000円で購入)
ロープで固定していきます。
思いっきり閉め込んでいき、
最後に真ん中で二重に編み込んでいきます。
3個も巻くと、両人差し指がこすれて、
真っ赤になりました。
右側は、鉾立小のターンバックルで締め上げた
ドラム缶太鼓。
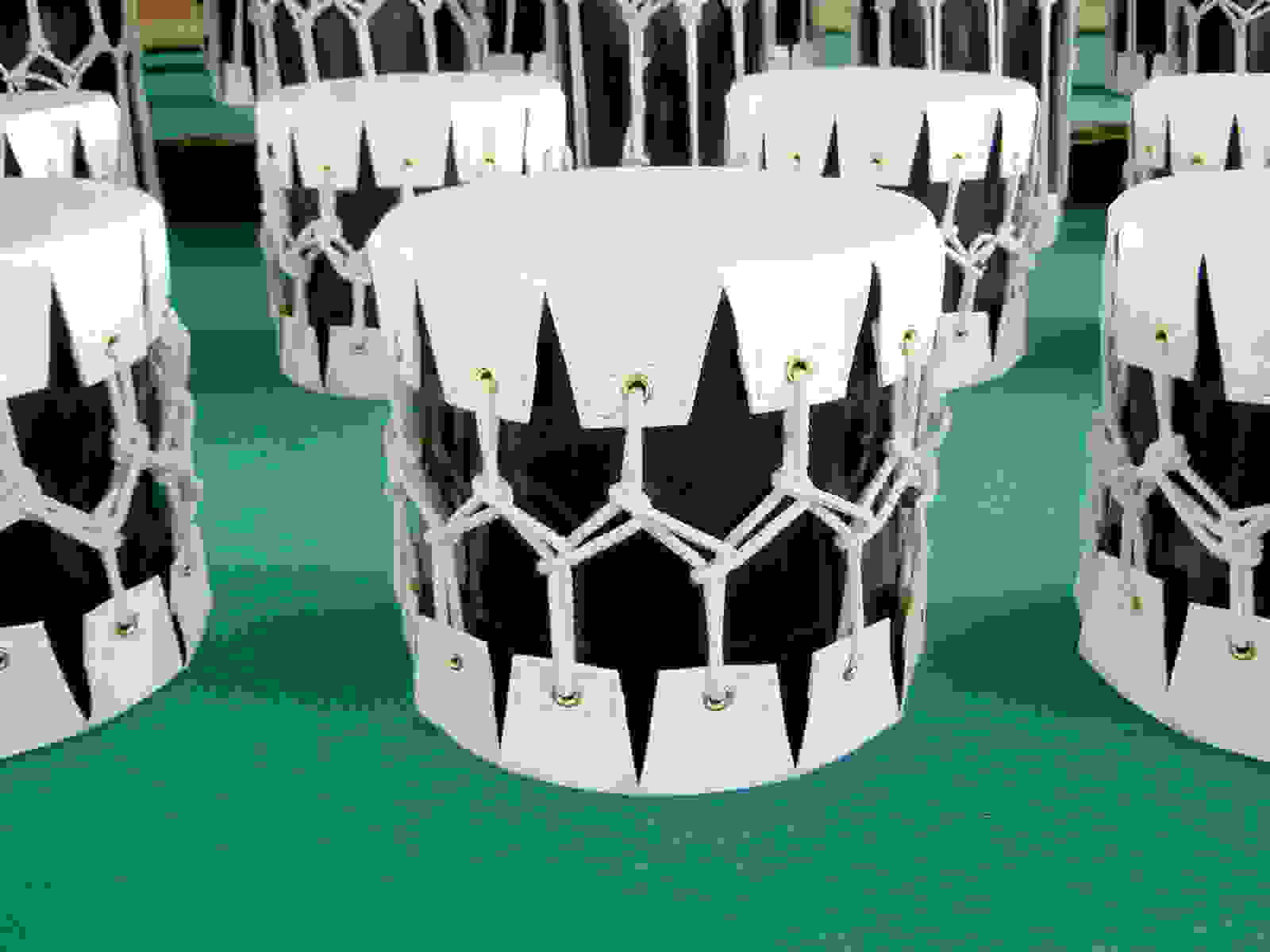
音の方は、80センチの高さのドラムの方が、
イメージ通りの重低音が出ました。
しかし、どちらも、
これから何度も締め直しをしないといけないでしょう。
30個もロープを締めると、
ちょうど真ん中で編み込む要領がつかめてきました。

5年生のあるクラス全員にたたいてもらいました。
なかなか30人が一斉にたたくことが難しいのに、
こうやってたたくと大迫力です。
子供たちは大喜び。
材料費は1個5000円以内に押さえることができました。

長ドラム太鼓では何度か打つうちに、
支えが強度不足でこわれ、
最終的に、この形に落ち着きました。

児島文化センターや、倉敷チボリ公園や、
その他、
呼松太鼓ジュニアの発表場所で
なくてはならないものになりました。

主に学校での音楽の時間や、
教室の学習発表会などで大活躍。

自ら濁流に使ったドラム太鼓は、
中がさびてきました。
そこで、さびを落として、
ペンキを塗ってリニューアル。
ついでに、皮も強く張りなおししました。