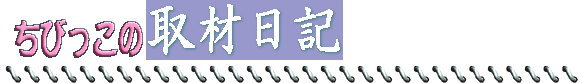
プール開き 2000.6.2.fri.

 6月に入り、各地の小学校でプール開きが行われています。
6月に入り、各地の小学校でプール開きが行われています。
下津井東小学校のプール開きの取材に行きました。
6年生が瀬戸大橋の見えるプールで、今年の初泳ぎ(?)を楽しんでしました。
6年生の目標は全員が25メートル泳げるようになることだそうです。(平泳ぎとクロール両方)
水温は23.5度、泳ぐにはちょっと寒いかな。
梅雨を前にがけやため池の視察 2000.6.5.mon.
岡山県では去年おととしと6月2日に梅雨入り宣言が出ているそうで
そろそろ梅雨に入ってもおかしくない季節になってきました。
倉敷市の水島地区では、
水島消防署・水島警察署・水島支所・臨港消防署の関係機関が
合同で災害警戒区域を現状視察し、大雨のシーズンに備えました。
倉敷市広江7丁目(水島インターから東に少し行ったところ)の、満池(みちいけ)は、
江戸時代に作られた古いため池で、大雨が降ると漏水する可能性があり、
豪雨の度に重点的にパトロールされているため池です。
土で突堤が作られているため決壊が心配なところ。
倉敷水島地区に改修工事待ちのため池が6ヶ所あって、
工事のための予算が下りるのを順番待ちしている状態です。
 また、大雨が降ると危険とされる急傾斜地(がけ)はたくさんあります。
また、大雨が降ると危険とされる急傾斜地(がけ)はたくさんあります。
おおむね、災害防止工事(落石防止や水の流れる溝を作るなど)が着工している所が多いようですが
地権者との話し合いがついてないところもあるそうです。
写真は広江7丁目コスモタウン南東の急傾斜地。
ためになるかもしれない話
岡山気象台の人に聞いた話だと
「梅雨入り」の予想というのは出さないそうです。
雨が降り続いた状況を見て「これは梅雨に入った」と宣言するそうです。
ちなみに今年の岡山県は、今週末に天気が崩れることが予想されることから
今週末にも「梅雨入り宣言」が出されるのではないかということです。(6月8日に梅雨入りしました)
総社市議会開会 2000.6.8.thu.
KCT(ちびっこがいるケーブルテレビ)では、総社市の市議会を収録してその日の夜に放送します。
今日は総社市議会6月定例会が開会しました。
五万人以上が住む総社市の市長は竹内洋二さん(51)。市長3年目です。
「黒塗りの公用車を売って市の財政の足しにする」と言ってみたり
「自転車で通勤」してみたりと、
市長自らが、枠にとらわれない行動をとることで、長年の慣習を破ろうとしているような市長です。
と、こうかくと、ぐいぐいと人をひっぱって行く大変精力的なたくましい市長かと思ってしまいますが、
竹内市長の見た目は、つぶらなひとみの小柄な男性です。
だからか、市長の行動は「スタンドプレー」に見えるようで、
市の執行部からも議員さんからも風当たりが厳しいようです。
でも最近は市の執行部とはうちとけたのか、協力している様子です。
とか思っていたのに。
今日は市長からびっくり発言が飛び出しました。
「収入役の岩田氏が、昨日、辞職願いを提出されまして、
私も留意を頼んだのですが、本人の意思は固く…」収入役が辞任しちゃったんです。
もともと市長は苦しい財政を少しでも立て直そうと、助役や収入役をたてない(!)という方針で市政をすすめていました。
しかし、そんな既存の制度を打ち破るような市長の姿勢に、みんな猛反対。
みんなの言葉に市長が折れるようなかたちで、やっと助役と収入役の3役が決まった所でした。
中でも収入役の岩田氏はただでさえ、「自分は収入役なんてとんでもない」と渋るのを市長が説得してやっと就任したのに、
議員からは過去を暴かれ、反対されて心労がたまっていたようです。
市長への風当たりの強さはそのまま3役まで飛び火してしまったのでしょうか…。
とにかく、市長の口から、「収入役辞任」が報告されたわけです。
慌てたのは市の一部職員、「聞いてない」というわけです。
まあ、先に事実が明かされていた幹部職員もいたのかもしれないのですが、
周りの職員さんからしたら「一言相談してくれても良いじゃん」といったところ。
情報は共有しておかないと、信頼関係を壊すことにもなるかと思いますので要注意です。
石原裕次郎特別展 2000.6.9.fri.
倉敷三越で石原裕次郎特別展が開かれています。
104本の映画ポスターや名場面の写真、小道具。台本などが展示されています。
 石原裕次郎は昭和9年神戸市須磨区うまれです。
石原裕次郎は昭和9年神戸市須磨区うまれです。
海の男(船乗りと言うのかな?)であった父の影響を受けて自分も船乗りになるのだと思って成長したようです。
しかし昭和30年兄で小説家(現在は東京都知事)の石原慎太郎さんが芥川賞を受賞し、翌年その作品「太陽の季節」が映画化されたとき、若者言葉の指導にと撮影現場に行った裕次郎さんは今でいうプロデューサーに見初められます。
そして慎太郎さんの次回作「狂った果実」で主役として衝撃的なデビューを飾ります。
以来、102本の映画に出演、歌手としては521曲もレコーディングしました。
また「西部警察」などテレビドラマシリーズでも常にヒットを飛ばしました。
石原裕次郎特別展は昭和62年にガンで亡くなった裕次郎さんを偲ぶ回顧展です。
 うえは映画「嵐を呼ぶ男」で裕次郎が打ち鳴らしたドラムセット
うえは映画「嵐を呼ぶ男」で裕次郎が打ち鳴らしたドラムセット
右は映画「太平洋ひとりぼっち」の撮影で使われたマーメイド号。
会場には裕次郎直筆の手紙なんかも公開されています。
「オス!」「ヤッ失礼」などと言う言葉がちりばめられていてステキです。
また石原慎太郎さん直筆で手を加えた「狂った果実」の台本も展示されていました。
裕次郎さんすごくかっこいいです。
石原裕次郎さんがお兄さんの石原慎太郎さんの芥川賞受賞作「太陽の季節」で初デビューを飾ったとは知りませんでした。その作品は慎太郎さん自身も出演されているんですね。
初期の頃は慎太郎さん原作の作品が多いんですね。いまさらですがスゴイ兄弟です。
この石原裕次郎特別展は倉敷三越開店20周年記念特別企画です。18日まで開催されています。
水島地区の少年剣道は強い 2000.6.10.sat.
水島警察署主催の水島地区防犯少年剣道大会がありました。
水島署管内の5団体の小学生中学生剣士たちが団体戦で戦います。
福田道場・昇龍館一福道場・水島武道館・連島スポーツ少年団・川鉄剣道スポーツ少年団の少年剣士たちおよそ200人が参加しました。
この大会で優秀と認められた選手ばかりで選抜チームが組まれ、
「水島警察署チーム」として岡山県警察少年剣道大会に出場します。
なんと水島署チームは2年連続県大会で優勝し、さらに、全国大会でも優勝しているそうです。
なんでも岡山県勢は強いと全国でも評判で、名指しでマークされている選手もいるとか。
水島署署長室に飾ってある優勝旗にそんな意味があったとは…はじめて知りました。
岡山では5年後に国体もあることですし、
選手たちにはぜひこのまま成長して剣道で良い成績をとってもらいたいものです。
総社市議会一般質問 2000.6.12.mon.
総社市議会の一般質問が始まりました。
一般質問では市民の代表である市議会議員さんが順番に市政についての疑問点などを質問します。
・病院の誘致問題について(総社市は、病床数の多い倉敷市が隣にあるので病院を簡単には増やせない)
・3歳児保育について
・建設が決まった吉備路観光センターについて
などの問題が総社市にはあります。
市議会議員さんは、市の行う事業について一生懸命勉強して
疑問点を質問したり、より良い事業になるように提案したりしているんですね。
(と信じてます)(?)
ところで、頑固者でファイト溢れる?総社市長ですが
今日はお昼の時間に自転車に乗って颯爽と市役所から漕ぎ出して行きました。
そう言えばこのまえの市議会で「市長が自転車で登庁するなんてふさわしくない」と非難を浴びていました。
市長はこの質問に「登庁の仕方くらい自分の思うとおりにさせてくれ」
「高梁川の自然などを感じて通勤することは大変頭がすっきりし、すがすがしい気分で執務にあたることが出来るのだ」
「中学生や高校生も自転車で通学している、危険なことは無い。交通ルールは守るから…」
などと答えていました。
今日の自転車姿を見ると、自転車通勤は許されたようで、市長は大変イキイキとしていました。
青いスポーツタイプでライトが二箇所についたかっこいい自転車でした。
育てる漁業を学ぼう~ひらめ稚魚放流~ 2000.6.13.tue.
 栽培漁業は‘採る漁業‘に対して‘育てる漁業‘です。
栽培漁業は‘採る漁業‘に対して‘育てる漁業‘です。
児島漁協は毎年この時期に
大畠漁港の大きな円形の水槽(直径8メートル)で稚魚を育て近くの海に放す「栽培漁業」を行っています。
岡山県牛窓の栽培センターから5月17日に譲り受けたひらめの稚魚が大きな水槽の中で中間育成(稚魚を外敵から身を守れるくらいにまで大きく育てること)され放流の時期を迎えました。
(巨大な水槽の中には44.5ミリの大きさに成長したひらめの稚魚が46.400匹います・写真ひだり)
社会科の授業で水産業について学ぶ倉敷市立下津井東小学校の5年生は
地元で行われている栽培漁業について学ぼうと大畠漁港を見学に訪れました。
ひらめは放流した所から比較的近い所に住み成長が速いため
放流効果が高く、栽培漁業に適した魚とされています。
今日は育てた稚魚を海に放しました。
半分は児島漁協の方々が船で沖のほうに放流しましたが
半分は子供たちが浜辺で放流しました。
 放流には大畠保育園・下津井幼稚園・阿津保育園の園児たちも参加しました。
放流には大畠保育園・下津井幼稚園・阿津保育園の園児たちも参加しました。
持ってきたバケツに稚魚を入れてもらうと、片方に目が二つついた独特の姿をしたひらめの稚魚を観察しながら
大事に海に放していきました。
栽培漁業は、近海を埋め立てたりしたため魚の産卵場所が無くなってしまったことに気づいた漁業者が
農業で種をまくように卵を孵して稚魚を海に放すことを思いついたことから始まり、
以来、採りすぎて海の魚を減らさないように、魚と人間が共に生きていけるようにと行われている「育てる漁業」です。
 家が漁業や漁業関係の仕事をしている子供も多く、(実際にひらめを採っている家も。)
家が漁業や漁業関係の仕事をしている子供も多く、(実際にひらめを採っている家も。)
子供たちは、海に、育み育まれている漁業について学んでいました。
本日の驚き
ひらめは孵化したときは
普通の魚と同じように前から見ると縦長の魚です。’┃’
しかし生後三十日間で片方の目が少しづつ反対側に移動し(!)
片方に二つの目があるひらべったい独特の姿になるそうです。’━’
目玉が移動するって無茶な話や。どうやってひれの所とか移動するんやろう?
清音村の花しょうぶ
 清音村役場西で、今ちょうど花しょうぶが満開です。
清音村役場西で、今ちょうど花しょうぶが満開です。
役場近くの馬渡地区(マワタリ・60軒)と西市場地区(13軒)の住民が大切に育てている花しょうぶは約70種4000株。
今年は廃材(古くなった木製の電信柱)を使って遊歩道も完成し、村民の憩いの場になっています。
平成9年3月清音村は「快適環境推進の村」として宣言しました。
馬渡と西市場はそれに賛同して、快適環境推進地域として花しょうぶを育てることにしたそうです。
花しょうぶの世話は手間がかかりますが、手間がかかるほど地区住民がしょうぶ園に集まる機会が多くなり
交流になっていいのだそうです。
ちょうど世話をしていた住民の方の話によると
今年は株分けをしてしょうぶを増やし、将来的には1万5000株450坪くらいの菖蒲園にしたいと思っているそうです(現在は200坪)。
婦人会におにぎりを作ってもらって菖蒲祭り(鑑賞会)をするのもいいなあと言っていました。
この菖蒲園を誇りに思っているようでした。素晴らしいです。
 また裏話ですが
また裏話ですが
このしょうぶ園は休耕田の有効利用として、
清音村長の江口さんが真備町長(実家は種苗園)の鎌田さんに頼んで菖蒲の株をわけてもらったとか。
二人は仲良しのようです。
清音村役場横のふれあいしょうぶ園の花しょうぶは
これからもまだまだ花をつけますが
全体的に花が咲いてみごろなのは今週いっぱいだということです。
梅雨の中休みに田植え 2000.6.14.wed.
今日は梅雨の中休みとも言える大変カラリと晴れた1日でした。
梅雨の晴れ間の1日に、郷内幼稚園の子供たちは、田植えを体験しました。
 郷内幼稚園の子供たちは幼稚園横の田んぼの一角(近所のたこ焼き屋高田音松さん所有)を借りて田植えをしました。
郷内幼稚園の子供たちは幼稚園横の田んぼの一角(近所のたこ焼き屋高田音松さん所有)を借りて田植えをしました。
植えたのはもち米の苗。年末には収穫したもち米で餅つきをします。
郷内幼稚園は地域の人の協力を得ていろいろな行事を行っており、
この田んぼも地域のおじいちゃんが早起きして水を抜き
園児たちが田植えをしやすいように下準備されていました。(おじいちゃん曰く6時半から準備したらしいです)
田植えは等間隔にしるしのついたロープを一本田んぼの上に伸ばし
ロープをずらしながら、しるしの場所に稲を植えるという昔ながらのやり方で行われました。
「3.4本の苗をまとめてもち、親指と人差し指と中指を添えてまっすぐに田んぼに下ろす」
と、農業を営む保護者や地域の人たちが、子供たちに教えていました。
 郷内幼稚園の園長先生曰く
郷内幼稚園の園長先生曰く
・たくさんの人の協力で田植えをできることに感謝すること
・田植えを実際に、目で見て手で触って体を通して体験すること
の2つを学ぶのが目的だそうです。
郷内地区では地域の支えで子供たちの心を育てているのですが
子供たちはそんな大人たちの思いを知ってか知らずか、
かえるを追いかけたり、顔から田んぼに落ちて大泣きしたり(のぞきこんでて行きすぎた)
泥の感触を楽しんだりと、おおはしゃぎで田植えをしていました。
田んぼは幼稚園の隣にあるので
園児たちは毎日通園する時に自分が植えたお米が成長するのが確認できます。
きっと子供たちは年間通してたくさんのことを学ぶのでしょう。
梅雨に入り田植えシーズン到来です。
工業排水で鯉が育つ 2000.6.15.thu.
6月は環境月間なんです。
岡山県では、工業排水で育てた鑑賞用の鯉を小・中学校に寄贈しました。
 「工場で使った水は鯉が住めるくらいきれいにして外に流してるんだよ」
「工場で使った水は鯉が住めるくらいきれいにして外に流してるんだよ」
というPRなわけです。
倉敷地方振興局管内では9校の小中学校に全部で115匹の鯉を贈りました。
総社小学校にはカルピス㈱岡山工場(所在地・総社市常盤)からの鯉10匹が贈られました。
私が通った大学でも工学部が同じように鯉を飼っていました。
実験で使った水を浄化していることをアピールしているわけですが、
いつの日か工学部から流れ出る水路に住む鯉が
全部白い腹を浮かせて死んでいたことがありました。
塩素とか硫酸とか洗剤とか、なに流すのか知らないけど、
実験に使うもんやから危険な薬品もつかってるんやろね。
 ですから、鯉の寄贈に参加してる企業はその一年間ちゃんと工業排水を浄化していたということを表すのでしょうか。
ですから、鯉の寄贈に参加してる企業はその一年間ちゃんと工業排水を浄化していたということを表すのでしょうか。
鯉にとって水は体の一部、人間にとっての空気と一緒みたいなものでしょう。
私も空気が異常で触れるとぴりぴりしたりイヤな臭いがしたらいややもんね。
鯉が育つほど工業排水はきれいな水なんやね。
ちなみに総社小学校の中庭は上から見ると大きな足の形をしています。
ひざの部分が築山の頂点になっていて、そこから井戸水をくみ上げ、足の先に流しています。
コイは脚の部分をかたちづくる池に放流されました。
「大地にしっかり足をつけてすくすく育つように」という意味だそうです。
市町村の父は何点?~父の日ばらプレゼント 2000.6.16.fri.
6月18日は父の日。
父の日にちなみ、農業後継者クラブの皆さんがバラの花を
地域の市長村長に贈りました。
各市町村長に「父親としての自己評価」を聞いてみました。
総社市 竹内洋二市長 60点
「父親としては…60点くらいでしょうか。(合格ですか?)ぎりぎりです。」
理想の父親像は「勝海舟の父、勝小松」
厳しい愛情溢れた昔ながらの父親が理想だそうです。
 清音村 江口猛村長(写真) 満点
清音村 江口猛村長(写真) 満点
「私はいつのときも自分が満足できるように行動している。
有森さんじゃないけれど、いつでも自分を誉めてあげられるくらいに(いつでも一生懸命だ)。
自分に満足しています。」
村長は「父の日より敬老の日」と自分で言っていました。
職員や学校の先生に対して
「仕事がしんどいなら、違う仕事についてほしい」という。
「しんどいと思いながら仕事をするのは、なによりも村民に悪い。子供たちに悪い。
公務員というのは「しんどい」と思って仕事をしてはいけない職なのだ」という厳格な村長。
真備町 鎌田頼靖町長 50点から7・80点
「子育てしていた昔は50点くらいでしたけど、今は70点から80点くらいじゃないですか」
娘二人は嫁いでいますが、毎年相談して父の日にはプレゼントをくれるそうです。
町長は最近ゴルフに凝ってるので、「今年のプレゼントはゴルフボールかな」と予想していました。
倉敷市 中田武志市長 60点
「良い様に言いたいですが、うーん、平均点以上だと思います。(平均点は60点らしいです)」
子育てをしているときに心がけたことは
子供を一人の人間として認め、いつでもまじめに正面から向き合うことだそうです。
今は子育てから離れ、倉敷市の父として、子供たちが健全に育つように努力していきたいとのことです。
大変個性的な首長たちですが、
このなかで1番ばらが似合うのは?」という問に
K松原先輩は「そりゃ、山根じゃろ(山根玉野市長)」。
白いジャケット白い靴の山根市長には確かに赤いばらがよく似合いそう…
ちなみに総社、清音、真備の首長にバラを送ったきびじ農業後継者クラブは
マスカットハウスの自動換気装置を独自に開発し、岡山県の農業大会で発表したところ
最優秀賞に選ばれたそうです。
8月に佐賀県で行われる全国大会に出場するんだって。もちろん初出場です。
地域の1日先生 2000.6.18.sun.
倉敷市立第二福田小学校六年生の総合学習のテーマは「人とのふれあい」
 今日は父の日、二福小では日曜参観が行われました。
今日は父の日、二福小では日曜参観が行われました。
六年生は「地域の人から学ぼう」と、地域の人を先生として招いて工作をしました。
開かれた授業は「編物」「裁縫」「竹とんぼ」「竹笛」の4つです。
編物では、鈎針を用いて「アクリルたわし」を、裁縫では「お手玉」を作りました。
(写真はアクリルたわしをの編み方を教わる児童・竹笛の完成品)
 今は既製品がたくさんあるから、おもちゃを自分で作る機会は余りありません。
今は既製品がたくさんあるから、おもちゃを自分で作る機会は余りありません。
作業には児童のお父さんお母さんも参加してよく、子供より鉤針編みに夢中になってしまうお母さんや、子供と一緒に工作に取り組むお父さんの姿も見られました。
普段とは違う親の姿も見ることが出来、良い授業参観になったんだと思います。
総合的な学習で学ぶ「人とのふれあい」。
人とのふれあいは、どこで学ぶのだろう。
そもそも学ぶものなのかな。むずかしい現代です。
走るスポーツオリエンテーリング 2000.6.18
オリエンテーリングってご存知ですか?
森のスポーツといわれているスポーツです。
地図とコンパスを片手に、丘陵地を含む平地にいくつか設置されたポイントをまわるんです。
私も何度か経験があります。
しかし、これが本来「走るスポーツ」だということをご存知でしたか?
スウェーデンで生まれたオリエンテーリングは、走ってポイントを巡り所要時間の短さを競う激しいスポーツなのです。
もともと日本に来たのは、東京オリンピックの数年前。
オリンピックが開催されるというのに、日本人があまりにも運動不足だったので、
とにかく動いてもらおうとオリエンテーリングを奨励したのが始まりだそうな。
たしかに、地図を見ながら、森を迷いながら、仲間と話しながら歩くのはとっても気持ちが良いものです。
 6月18日は父の日!家族で楽しくオリエンテーリングを楽しもう!と、
6月18日は父の日!家族で楽しくオリエンテーリングを楽しもう!と、
全国一斉オリエンテーリング大会が開かれました。
岡山県大会は今年は倉敷市水島緑地福田公園を会場に行われました。
オリエンテーリング大会では、29のポイントを探し出し巡ります。
そのオリエンテーリング大会の取材に行ったところ、
選手たちの動きが速い速い。
各選手1分づつずらしてスタートするんだけど、
ものすごい勢いで目標を探して、目標に設置されているオリエンテーリング用パンチで通過のしるしをゲットしていきます。
私は一斉に駆け出していってしまった選手たちを目で追いおろおろ。
仕方なく自分で読図して公園内のポイントを探し出し、そのうち来るであろう選手達を待つことにしたのです。

 ちょっとしたオリエンテーリング体験だったけれど
ちょっとしたオリエンテーリング体験だったけれど
小さな目標(この場合は旗のような赤と白のしるし)を、小さな地図を頼りに探し出すことは大変難しかった。
(ちなみに写真は目標の旗と、その旗がある風景です、旗、どこにあるかわかりにくいでしょう?)
選手たちも走りながら右往左往。私も感心しながら右往左往。
オリエンテーリングは走るだけではダメ。地図を見なくてはいけません。
かといって考え込んでいても前に進めません。
頭に血が上っていては地図を読み間違えてしまいます。
他の選手を出し抜いてうまく目標を見つけなくてはいけません。
粘り強い体力と冷静な思考能力、強い意思が必要です。
しかも空気はおいしいし、自然は気持ちいいし、さわやかなスポーツやね。
今度どこかでオリエンテーリングしてみたいなあと思いました。
安養寺のアジサイ 2000.6.19.
倉敷のアジサイ寺、倉敷市浅原の安養寺でアジサイが色付きはじめています。
 安養寺には70種4000株のアジサイが植わっているそうです。
安養寺には70種4000株のアジサイが植わっているそうです。
アジサイはねえ、雨が降るほど色づくらしく、
今はまだ色づき初めという感じ。
今年は梅雨に入るのが遅かったため、8月初旬まで花が見られるのではないかとのこと。
アジサイは、色がたくさんあって、とてもきれいね。
色がいろいろ変わることから、花言葉は「移り気」。
大人のような、子供のようなイメージの花です。

 ところで、
ところで、
安養寺は、その名も「浅原山毘沙門天本山」
その門は、宝船を思わせる船の形をしていて(階段の真ん中には巨大ないかりがある)、
その船には、宝船の舵取りだったといわれる巨大な毘沙門天様が鎮座しています。
その他の六神も隠れるようにひっそりとそばの丘に立っています。
外から浅原山を見るとちょっとびっくりするような姿です。
新興宗教のような、神話の世界のような、見方を変えると宇宙的にも見える。
下に、安養寺作詞の歌(抜粋)を紹介します。
笑う門には福来る(災難除け万才唄)
一.恵比寿 大黒 毘沙門天 、寿老人に福禄寿、弁天さまに布袋さま、
7つの神様 福の神
笑う門には福来る
四.お宝船の舵を取る、毘沙門さまは船頭神、
生活金品使い方 恵比寿 大黒 乗せる神、
お宝船にみな乗せて 笑う門には福来たる
六.済んでしまった昨日は言うな、まだ来ぬ明日をわずらうな
笑い絶やさぬ家つくれ
毘沙門さまは家の神 笑う門には福来る
七.七福神々人に着く、笑って過ごせば七福神、
毘沙門 三文字御名呼べば 命と金と時間来る
3つくるくる 三つ巴 笑う門には福来る
八.父親毘沙門 金の神、母親吉祥 命神、子供禅尼師 時間神
子供に運つけ 運の神、百代続いて家繁盛、
百体毘沙門 吉備の神 笑う門には福来る
(ちなみに10番まであります)
「皆さんで声をそろえてお唄いください。元気になります。法主拍掌」
集団密航対策訓練 2000.6.26.
児島警察署が集団密航事件を想定した訓練を実施しました。
集団密航といえば、岡山県では、平成10年の牛窓港集団密航事件です。
岡山県ではそれ以外には発覚した密航はないようですが、
全国的に集団密航は爆発的に増えていて、毎年倍倍くらい増えています。

児島警察署の訓練は、
「琴浦港に不審な船が停泊し、迎えにきた保冷車に怪しい外国人風の人間が次々乗り込んでいる」
という民間からの通報があった、という想定で始まりました。
児島警察署では、そのような事態に遭遇すると
船や車(白バイ含む)を使って検索し、交番前や要所要所では検問を行います。
取材では警備艇に乗せてもらいました。
 そして訓練では、児島インターチェンジで、怪しい保冷車が捕獲され、
そして訓練では、児島インターチェンジで、怪しい保冷車が捕獲され、
なかから中国人の男女六人が出てきて逮捕されます。
いまのところ密航者のホトンドは中国人のようです。
この訓練は、集団密航だけでなく、
最近多発している凶悪犯罪に備える意味もあるそうです。
児島署管内には四国への通り道、瀬戸大橋があり、インターチェンジもありますから。
そう言えば、邑久町のバット少年は、四国に逃げているという説もあるとか…。
訓練が役に立つ事態にはあまりなってほしくないですね。
スリランカから真備町を視察 2000.6.29.
 スリランカの国会議員チュラバンダラさんが真備町を視察しました。
スリランカの国会議員チュラバンダラさんが真備町を視察しました。
チュラバンダラさんはスリランカ クルネガラ州選出の国会議員です。
クルネガラ州では、低所得農家の収入を増やすため、
州の川や運河沿いに竹を植えるプロジェクトを進行しており、
今はその竹を使って工芸品を生産し、農家の収入増のつなげようと研究しています。
ですから、竹産業のさかんな日本の真備町を視察したのです。
スリランカでは竹は建築の足場に使ったり、竹ざおにする以外使いみちを見出していないそうです。
たけのこも食べないんですって。
竹林はなく、根っこが強い特性をいかして、治水のために川沿いや湖のほとりに植えられているそうです。
チュラバンダラさんは、真備町内の竹林や竹炭窯、竹工房、たけのこ加工場などを見学しました。
まきび公園の中にある竹工房では、竹工芸同好会の皆さんが竹細工を作っています。
真備町がいきがい作りのために奨励している工房です。
竹の表面から文字や絵が浮き出すように作った作品は浮き彫りの作品です。
微妙に傾けた「糸鋸版」に竹を設置していとのこで模様や文字を切りぬいていくと
不思議なことに、右回りだと浮きあがり、左回りだと模様が沈んでいきます。
私はこの作品は、磨いた竹に字や模様を張りつけているのかと思っていましたが、
はめ絵のように一本の竹で出来ているんです。
これは芸術だ。私はびっくりしました。
竹といえば真備町。その名声はスリランカまで届くのだ。
シネマセンシュー120年の歴史に幕 2000.6.30.
 倉敷市阿知の映画館「シネマセンシュー」が閉館しました。
倉敷市阿知の映画館「シネマセンシュー」が閉館しました。
 シネマセンシューは明治14年に芝居小屋「千秋座」として創業発足し、
シネマセンシューは明治14年に芝居小屋「千秋座」として創業発足し、
大正から昭和へ変わる時に映画館となりました。
昭和三十年代の映画黄金時代
そのあとのテレビの普及で他の映画館が閉まる中、
映画黄金時代再来を信じて興行を続けました。
しかし、モータリージェイションの現代、、
駅前の映画館より
駐車場のある郊外の映画館の客の好みが変わったことから、
2000年6月30日の9時5分の上映を最後に
120年もの歴史の幕を下ろしました。
映画館閉館は倉敷の都市開発事業にも関係しており、
建物はアパートになるとか。
町の映画館は文化の発信地。
倉敷の町に映画という夢を運んできた映画館の閉館はさびしいですね。
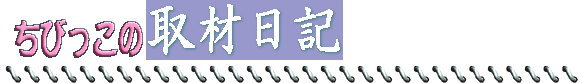
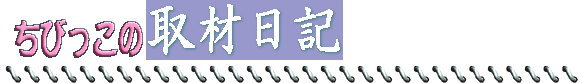
 また、大雨が降ると危険とされる急傾斜地(がけ)はたくさんあります。
また、大雨が降ると危険とされる急傾斜地(がけ)はたくさんあります。 石原裕次郎は昭和9年神戸市須磨区うまれです。
石原裕次郎は昭和9年神戸市須磨区うまれです。 うえは映画「嵐を呼ぶ男」で裕次郎が打ち鳴らしたドラムセット
うえは映画「嵐を呼ぶ男」で裕次郎が打ち鳴らしたドラムセット 栽培漁業は‘採る漁業‘に対して‘育てる漁業‘です。
栽培漁業は‘採る漁業‘に対して‘育てる漁業‘です。 放流には大畠保育園・下津井幼稚園・阿津保育園の園児たちも参加しました。
放流には大畠保育園・下津井幼稚園・阿津保育園の園児たちも参加しました。 家が漁業や漁業関係の仕事をしている子供も多く、(実際にひらめを採っている家も。)
家が漁業や漁業関係の仕事をしている子供も多く、(実際にひらめを採っている家も。) 清音村役場西で、今ちょうど花しょうぶが満開です。
清音村役場西で、今ちょうど花しょうぶが満開です。 また裏話ですが
また裏話ですが 郷内幼稚園の子供たちは幼稚園横の田んぼの一角(近所のたこ焼き屋高田音松さん所有)を借りて田植えをしました。
郷内幼稚園の子供たちは幼稚園横の田んぼの一角(近所のたこ焼き屋高田音松さん所有)を借りて田植えをしました。 郷内幼稚園の園長先生曰く
郷内幼稚園の園長先生曰く 「工場で使った水は鯉が住めるくらいきれいにして外に流してるんだよ」
「工場で使った水は鯉が住めるくらいきれいにして外に流してるんだよ」 ですから、鯉の寄贈に参加してる企業はその一年間ちゃんと工業排水を浄化していたということを表すのでしょうか。
ですから、鯉の寄贈に参加してる企業はその一年間ちゃんと工業排水を浄化していたということを表すのでしょうか。 清音村 江口猛村長(写真) 満点
清音村 江口猛村長(写真) 満点 今日は父の日、二福小では日曜参観が行われました。
今日は父の日、二福小では日曜参観が行われました。 今は既製品がたくさんあるから、おもちゃを自分で作る機会は余りありません。
今は既製品がたくさんあるから、おもちゃを自分で作る機会は余りありません。 6月18日は父の日!家族で楽しくオリエンテーリングを楽しもう!と、
6月18日は父の日!家族で楽しくオリエンテーリングを楽しもう!と、
 ちょっとしたオリエンテーリング体験だったけれど
ちょっとしたオリエンテーリング体験だったけれど 安養寺には70種4000株のアジサイが植わっているそうです。
安養寺には70種4000株のアジサイが植わっているそうです。
 ところで、
ところで、
 そして訓練では、児島インターチェンジで、怪しい保冷車が捕獲され、
そして訓練では、児島インターチェンジで、怪しい保冷車が捕獲され、 スリランカの国会議員チュラバンダラさんが真備町を視察しました。
スリランカの国会議員チュラバンダラさんが真備町を視察しました。 倉敷市阿知の映画館「シネマセンシュー」が閉館しました。
倉敷市阿知の映画館「シネマセンシュー」が閉館しました。 シネマセンシューは明治14年に芝居小屋「千秋座」として創業発足し、
シネマセンシューは明治14年に芝居小屋「千秋座」として創業発足し、