11 歪みの表出、問題行動
(心理的ゲームの分析)
ケーススタディー
「はい……、でも……」
社 員 来期の教育計画どうしましょうか?
課 長 うん、早く計画をたてないと、また先生のスケジュールの確保や会場探しで苦労する
ことになるよ。
社 員 そうですね。本当に早く決定していただきたいんですけどねぇ。
課 長 おい、おい、計画を立てるのは、君の役目じゃないのかね。
社 員 でも、予算が決定されないと、日程計画の決めようがないんですよ。
課長から、部長に予算がどうなるか聞いて下さいよ。
課 長 もう君も一人前の担当者なんだから、それ位のことは自分で処理しろよ!
社 員 ええ、でも………、多分、部長も自分だけで予算を決められるわけではないから、何と
もおっしゃれないんじゃないですかね。
課 長 それはそうだよ。
杜 員 でも、先生の確保や、会場の確保はどうしますか? 叱られるのは担当の私ですから……
先にやってもいいですか?
課 長 やっぱりそれはまずいよ。予算が決定されてからでないと………。
社 員 そうしたら、計画の方はどうしましょうか?
この2人の会話は、何かもやもやとした気持ちが残り、すっきりとした話になっていませんね。
社員の方には、「上司がちゃんと条件を整えてくれないからうまくいかないんだ!、ルールや
規則、手続きばかりにとらわれていたら、仕事なんか出来ないじゃないか」という思いがあり、
課長の方には、「制約された条件の中でも、うまく状況を切り開いてやってこそ、中堅というも
のだよ!」という思いがあるようです。
それを、お互いが隠してしまっていて、うまく伝え合えていないのですから、2人の間の会話は、
いつでもこんな具合に、パターン化された、噛み合わないものとなってしまいそうです。こうした
係わりを、心理的ゲームといいます。
心理的ゲームとは(グールディンクの定義)
・屈折した問題性のある対人関係、生き方のパターン
・本人も知らず知らずのうちに陥ってしまう。(Aで明確に気づいていない)
・心の奥底では、本当に言いたいこと(「……はOKじゃない」)を持っているので、隠された
やりとりで展開される。
・結未では、“もやもやした感じ”や悪感情が残り、「やっばり……」とつぶやく。
・何度となく繰り返して行われる。
ゲームは理解することが難しい
心理的ゲームは、日本では“遊び”と言う意味合いの強い言葉の“ゲーム(GAME)”という
言葉が使われることにより、それに惑わされて、逆に、理解することが難しくなっていると言え
ます。
“ゲーム”と言う言葉の本来的な意味合いは、“繰り返し行動”のことです。
子供の遊びのゲームをよく観察してみると、同じようなことを、何度も繰り返してやっています。
時々、気分や雰囲気、その場の状況やメンバーの誰かの動きなどによって、動きのプロセスや結果
は、少しずつ変化してゆきますが、全体を通しては同じような行動が、何度も繰り返されていきま
す。
この繰り返し行動に“心理的”と言う言葉がついているのは、「心の歪みが原因で起きる」こと
を意味しています。 “ゲーム”は、上記に説明したとおり「心の歪みが原因で起きる、何度も繰り
返えされる、問題のある、態度・行動・生き方」です。
もともとは、 エリック・バーン博士が、心の病気に陥った人の治療のプロセスで、患者の行動
を観察していて気づいた“パターン化された問題行動”だったのです。TAの成り立ちの出発点は、
“心理的ゲームの考察”にあったのです。
こうしたことを踏まえて理解すると、幾分でも、理解が進むと思います。
ゲームは人柄の歪みの表面化した“問題行動パターンの現われ”
心理的ゲームは、知らず知らずのうちに演じてしまうもので、当人は全く気づいていません。
これは、無意識的な、人柄の歪みの表面化した“行動パターンの現われ”なのです。
子供の頃に、人柄(感情・感覚の感じ方の傾向性、表現・態度・行動の表現の仕方の傾向性)を、
歪められたり、傷つけられたりするディスカウントを経験しないで育った人など、誰一人としていま
せん。ですから、人は多かれ少なかれ、ディスカウントを受け、人柄の中に、歪みや問題性を作り、
大人になってもそれを持ち続けています。 しかし、そうした自分の歪みに気づいている人は、極めて
少ないといえます。
また、たとえ、どこかで歪みに気づいていても、“見つめたくない、認めたくない、知られたくな
い、触れられて傷つきたくない”ために、多くの人がそれに蓋をしてしまいます。そしてさまざまな
理由をつけて、自己正当化をして、自分をごまかしてしまうのです。
でも、こうした心の歪みがある限り、何かの時には、この歪みに基づいた問題行動をとってしま
うことになるのです。しかも、その歪みに気づき、それを直さない限り、依然として歪みを持ち続け、
時に、あるいは、しばしば、バランスを欠いた行動や感情に引きずり回され、自分や他の人を巻き
込む人間関係のトラブルや、同じような問題行動を繰り返すことになるのです。
これが心理的ゲームなのです。
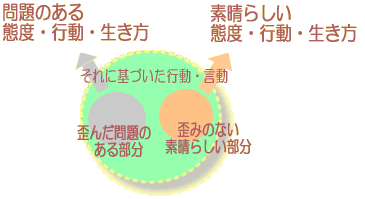
心理的ゲームは、何処でも演じられている
現代社会は、よくいえば、経済的にゆとりが出来、個人の自由が認められる状況になってきました。
ところが、反面では、このゆとりや自由さにより、“モラトリアム化、人柄の未成熟化が進み、強い
自己主張が許され、わがまま勝手も許され、それが堂々と横行する状況”になってきています。
人柄の未成熟化は、また一方では、良い人間関係を作り、維持する能力が落ち、浅く、薄く、表面
的な関係しか持てず、自分の本当の気持ちを隠して人間関係を持とうとする風潮を助長したのです。
人々のセルフコントロールの能力が落ちると、歪みの表出を抑えることが出来ず、心理的ゲームに
なってしまいがちになるのです。こうしたことから、私たちの周りでは、家庭でも、職場でも、至る
所で、気がつかないうちに、沢山の心理的ゲームが演じられ、人間関係のトラブルが増えることにな
っているのです。
次のような出来事も、その多くが、心理的ゲームであったりします。たとえば、
家庭の中の夫婦喧嘩、
親子の言い争い、
職場の上司と部下との衝突、
営業の接客応対でのお客とのトラブル、
組織の中の部門間の勢力争い、
労働争議の労使のぶつかり合い、
ライバル関係の会社同志の市場の奪い合い、など。

