5 PACの2つの分析
(機能分析と構造分析)
ケース・スタディ
近所の3歳ぐらいの女の子が、我が家へ遊びに来て、ダイニング・テ−ブルの上に
ある到来物のクッキ−の箱を見つけると、実に明るく「ねえおばちゃん、これクッキ−
だよね。とってもおいしいんだよね。でも歯が痛くなるから、食べちゃいけないんだ
よね!」と言い、妻の顔をじっと見詰めるのです。
すると妻は「でも内緒でおばちゃんと三つだけ食べちゃおう!、ママには内緒ね!」
と言うと、本当に嬉しそうな顔をして、「ありがとう、ママには内緒ね」と言って、
おいしそうにクッキーを食べるのです。
さて、この女の子は今、どの自我状態にあるのでしょうか?
“小さな教授”
表面的にみると、明らかに自然のC(FC)です。しかし、なにか子供ながらの鋭い直感と知恵を
働かせているようです。以前にどこかでTAを勉強された方で、これが“小さな教授”という自我
状態だと教わった方もあるのではないでしょうか。
“小さな教授”というのは、『負うた子に教えられ』といったような、大人が子供から教えられる
ところがあるような人柄の部分なので、このような名称がつきました。この部分は、幼児の持ってい
る、“ひらめく知恵のような部分”です。直感力に優れ、創造的でもあり、知恵を働かせて大人を
動かすような頭の良さを見せるので、かなり A の要素も感じます。しかしやはり全体的に見ると C
です。
もう一つの自我状態分析(構造分析)
さて、今まで説明してきたところには“小さな教授”という自我状態はありませんでした。では、
それは、何故なのでしょうか?
実は、自我状態の分析には、違った観点からの、二つの分析の仕方があるからです。“機能分析”
と呼ばれるものと、“構造分析”と呼ばれるものです。
今まで説明してきた自我状態の分析の仕方は、“機能分析”と呼ばれるものです。それは、ある人
を外側から観察していて、どのような態度、言葉、表現、行動がみられるか、つまり、自我状態が
どのような働き(機能)をしているかの視点に立って、分析する仕方です。
それに対して“構造分析”と呼ばれる分析の仕方は、その人の自我状態がどのような過程(歴史)を
経て、どのように形成され、発達していったか、という視点に立って分析する仕方です。
最初の女の子のケースに戻って考えてみましょう。
この女の子の自我状態は全体的に見ると子供の自我状態、C ですが、どうも子供の知恵といった A
のようなものも、母親から教え込まれた観念、P のようなものも、働いているようです。
構造分析による考え方では、子供の自我状態、Cの中には、将来発達して P になる要素 “P1”が
あり、また、将来発達して A になる要素 “A1”があり、本来的な素質、感情、感覚、欲求の塊で
あるCの元、 “C1”があり、この3つで C が成り立っていると考えます。
そしてP1 が発達して、本当のPになるのですが、発達を表わすためにPをP2 と表記し、同様に
発達してできあがる A をA2 と表わし、PACの元でなりたつ C を C2 と、表わすことにしました。
構造分析による人柄の発達を図示して、機能分析との関連づけをしてみるとの下図のようになります。
機能分析は、“ 自我状態の分析 ”や “ 対人関係、やりとりの分析 ”などを説明しやすく、構造分析
は、後に出てくる “人生脚本の分析 ” などの説明に使われます。
TAの創始者、エリック・バーン博士は、二つの分析の仕方をごっちゃにして混同すると混乱を招く
と、混同を戒めましたが、説明のしやすさから、混同して使う研究者もいるので、ちょっと混乱し
てしまうことになるのです。
(下図参照)
構造分析の自我状態分析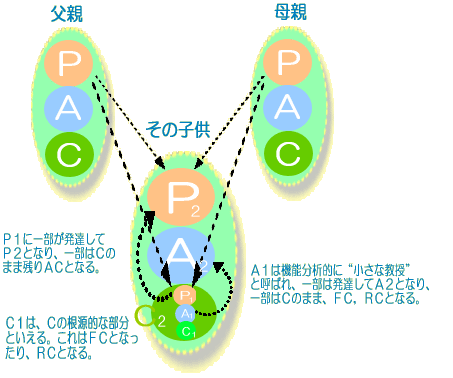 |

