|
7.6つの自我状態によるエゴグラム (1)エゴグラム分析の意味合いとは エゴグラムとは 人柄を構成する6つの要素が、その人の中にどれくらい存在し、どれくらい表面的な、態度や 行動に現れてくるかをとらえ、それを数量化して、その人の人柄をグラフ化して表すのがエコグ ラムです。 エゴグラムを見ると、どのような親の人柄の影響で、どのような人柄が形成されてきたか、その 結果として、今、どのような態度、行動、対人反応などをとりやすいかなどが、おおまかですが、 つかめるのです。 何のために“エゴグラム”を描くのか 人柄というものは、見方によっていかようにも見え、また、相互関係によって様々に変化する ものです。それに、私たちの人柄、パーソナリティーは、成長も退行もします。これを表すエゴグ ラムは、いつも変わっていくものだと考えて下さい。 そもそも、“自我状態”という考え方は、『人は瞬間、瞬間において変化する』事を前提にして いるのですから、“今ここにおける自分の状態の把握”こそ,、最も重要であることを忘れないで 下さい。こうしたことを踏まえた上で、「何のためにエゴグラムを描くのか」を考えて見ましょう。 ① 当人の自己認知や自己チェックによって描かれるものゆえ、それには多少の歪みや不正確な 部分が含まれている。それでも、当人の人柄の傾向性を大まかに捉えることが出来、自分で 自分を見直す手掛かりが得られる。 ② 周囲の人達に、当人を理解するための大きな手掛かりを提供する。 ③ 自分の人柄の特徴を知り、どの部分を伸ばし、どの部分を抑え、どう自己成長を図るかの指針 が得られる。 ④ 相手や周囲の人達のエゴグラムを描いてみると、その人の人柄の傾向性がつかめ、どのように 関わったら良いかを、事前に検討できる。 ⑤ TAを学んだ人同志がエゴグラムの交換をすると、自分に思う自分と、相手から見た自分の一致 やズレが確かめられる。 ⑥ 共通に知っている第三者を描いて見せ合い、話し合ってみると、その人に対する認知の仕方の 違いを明確に出来たり、見方のズレ、認知の仕方のズレを埋め合わせることが出来る。 “エゴグラム”の分析で、一番留意すべきことは “エゴグラム”を取り扱う上で、一番大切なことは、“ エゴグラム ”は、当人の感覚で描いた ものにせよ、チェックリストによって決められた方法で数値化された枠組みに沿って描かれたもの にせよ、これはあくまでも“当人の自己認知によって、作り出されたもの”で『自分は自分のこと を、こんな人間であると思っています』と言って提示するイメージで、それが正しいという保証は、 何も無いということを、しっかりと自覚して置くことです。 はっきり言えば、当てにならないのです。それでも、当人はそう思っているのは事実なのです。 “エゴグラムの正確度(信頼度)”は、その人の成長度合いで決まる 何故かというと、未成熟な人や自己中心性が強い等の、大きな問題性のある人は、大体において、 自分についての正しい認知が出来てな無いことが一般的です。 自己認知が、思い込み、強い不安・恐怖・怒りに基づいたものであったとしたら、自分の力や能力を、過剰に大きく見たり、反対に、過剰に過小評価をしたりしているので、“自己認知”が全く当てにならないのは、当然の話です。 こういう人は、その周囲にいる人達に、『当人は自分のことを……と言ってますが?』 と聞いてみると、『正反対ですよ!』、『あきれた!』、『それは嘘でしょ!』と反応します。 人格的に成長している人は、一般的に、“知的な能力”も高く、人柄的にも、周囲の人達から尊敬の念を持って見られているような人でしょう。こういう人達は、多くの人と出会い、いろいろな体験を深め、人、物、出来事、社会の仕組み等の、様々な領域の出来事にも、高い視点を持ち、広くて深い洞察力があります。 対人関係では、人の話が聞け、人の気持ちを受け止めることができ、そして、自分にとって耳の痛いことも、感情的にならずに、耳を傾けることが出来ます。 また、自分の情感も豊かで、周囲を楽しませたり、喜ばせたりもします。 こういう人達の自己への認識は正しく、周囲の人達の、誰に聞いても『そう、その通りです!』と言うでしょう。 最も重要なことは、その正確度の検討から、行動の変容へ繋げること 特に重要な“エコグラムの解析の意味合いは、結果として出てきたエコグラムが、どれ程正しく描かれているか、その正確度を分析、検討することにあります。 “エコグラムによる自己認知”の正確度は、『その人の人間的成長の度合いを示している』からです。これをチェックする具体的方法は、当人の周辺にいる人達に、TAの、“自我状態の分析”の理論を理解していた だき、自分が見るその人を、TAの“エコグラム”の概念を用いて表現してもらうのです。 “自己分析だけによる自己恕知”にはどうしても限界があります。この限界を乗り越えるのに鮭、その人の周囲にいる、正しく人柄を見ることが出来る成熟した人達から『認知のフィード・バック』を貰う方法以外にはありません。 自己認知と、他者からの正確度の高い情報のフィードバックで“その認知のずれ”が有るかないか”を見るのが、最も良い方法です。ズレが有るんじょならば、どういう面での、どの程度のズレなのかを、当人がしっかりと認知し、更に、そのズレを埋めるために自分が何をしたら良いのかを考え、それを自分の日常の行動パターンにできるように、自己変容すると同時に、周密の人達も、その“自己変革・自己成長”をサポートするような集団の相互作用があれば、それこそ人間的能力の高い人を育てる環境といえます。 この点からいえることは、TAは、ファミリー・グループによる研修会で学んでいただくことが『最も人間成長を促す結果に結びつ<』展開の仕方です。 (2)エゴグラムの基本的類型の解説 一般的な人柄のパターン分析は (エゴグラムのパターンの解説) (1)ハの字型(山型、丘型、M型)
両親の双方、あるいはいずれかが大変優しい人だった家庭の 中で、自由にのびのびと育てられた人に見られるパターンです。 昭和40年以降の生まれの”新人類”といわれる人達には多い パターンです。 人柄としては優しさ、明るさ、無邪気さと素晴らしい面を持 った人といえます。しかし、Aの低いM 型といわれるパターン になると、うまく状況や場面 に適応できず、感情や気分によっ て行動しがちになるといえます。 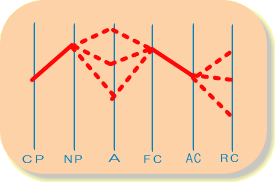 (2)逆ハの字型(W型、鍋底型、∨型)
このパターンは両親の双方、あるいはいずれかが厳格か、 自分の理想や信念をしっかりと持っていた人だったという 家庭に育った人に見られるパターンです。 昭和30年以前の生まれの旧人類といわれる人たちの中に よく見られる パターンです。 人柄としては親から受け継いだ価値感、理想、信念などの 強い人で、自己規制の枠組が強く、時にはくそ真面目と言わ れるくらい生真面目な人といえます親になったり、役職につ いたりすると、いつの間にか人に厳しく、批判的になりがち ですし、この傾向が強くなりすぎると、自分に圧力をかけす ぎることにもなります 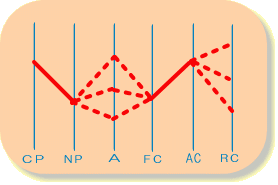
(3)N 型
どちらかというと母系的といえるパターンの人で優しくて 従順な母親(あるいは父親)をモデルとして自分の人柄を形 成した人のパターンといえます。 このパターンの人は自分の気持を抑えて人に優しく振舞う 人なので、表面的には対人関係でのトラブルや問題は全く起 さない、穏やかな人といえます。しかしながら内的には自分 の欲求や感情の発散を抑えるのでストレスをためやすく、あ る場合は身体症状として現れるかもしれません。 このパターンの人でAの低い人は問題解決力が落ちること となり、優柔不断、頼りにならないなどと言われることにな 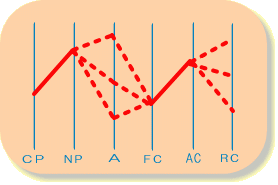 ります。 ります。 (4)逆 N 型
N型とは全く反対のタイプで、父系的とも言えるパターン の 人で、厳格な父親(あるいは男まさりの母親)をモデルとして 自分の人柄を 形成した人のパターンです。 このパターンの人は、良く言えば自由闊達、悪く言えば我が ままな面と人しての責任感や信念を持ち、社会や家庭の中で、 きちんと役割を果たしていく姿勢の両方を持っている人です。 どちらかというと古いワンマンタイプの人といえます。強い 信念、達成欲求、反発心を持っているので、大きなエネルギー や力を発揮する人ですが、平和な安定した社会や組織では力を 出し過ぎて、トラブルメーカーとなるようなこともあります。 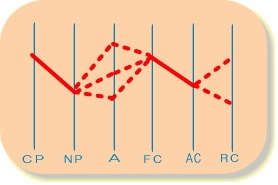
(5)フラット型
親のあるいは両親の厳しさと優しさのバランスのとれた家庭 の中で育ったパターンといえます。どの人柄の要素も全て持っ ており、どのような状況にも、どのような人にもうまく適応で きる、大変安定したよい人柄といえます。 しかし、別の角度から見ると、インパクトが乏しく、これと いった個性の乏しい人、八方美人などと言われることもあるか もしれません。 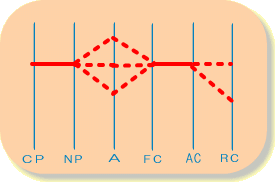
自分の人柄(エゴグラム・OK図表)を知るのはここから
(株)ヒューマンスキル開発センターの「TA PACK SYSTEM」をお薦めします。 |

