9 ディスカウントで形成される人柄の歪み
人柄の歪みとは
私達は、時として、「エッ!」、「おや?」、「あれ?」、「何で!」、「どうして?」と言わ
ざるを得ないような、相手からの刺激や反応を受けることがあります。こうした時というのは“相手
や自分の人柄の歪み”に晒されているときなのです。
“人柄の歪み”は“問題のある物の見方、考え方、感じ方、反応の仕方、行動の仕方、生き方”
として表れてくるのです。人柄の中にこうした歪みを作るものは、子供の頃の親や親的な大人から
のディスカウントの係わり方の刺激なのです。
ディスカウントとは
“ストローク”とは、“相手の人(自分)の存在、価値、あるいはその行為について、それを
認めていることを伝える、何らかの働きかけ”であると定義されています。その反対が“ディス
カウント”です。
その意味は、まさに、“値引き”で“相手(自分)の存在、価値、あるいはその行為のあるが
ままを認めずに、小さく見たり、存在しないものと見たりして、その値引きをする”のです。
さらに詳しい定義
“相手や自分、さらにはそれをとりまく状況などについて、それを軽視したり、無視したり、
傷つけたり、その存在を破壊的に否定するような、物の見方、感じ方、心の持ち方、そしてその
具体的な表現、行動”ということになります。
もう一つ、別の観点からとらえてみると
“ディスカウント(Discount)”という英語の単語の意味は“極小視”です。
相手や自分、私達をとり巻く周囲の状況や事実について“何かを、実際以上に小さく見ようと
する心の動き(メカニズム)”をいいます。
自分に危害を加えそうなものや、傷つけられる可能性があるような刺激が身に迫った時、それを
まともに見てしまうと、大変な恐怖を感じます。そんな時、それをまともに見ないですめば、自分
の安定を守ることができます。この自己防衛のメカニズムが“極小視”なのです。
“極小視”のメカニズムが働く時には、それと同時に、何かを実際以上に大きなものと見よう
とする“誇大視” (Grandiosity)のメカニズムも働きます。自分にとっての危険や恐怖を、実際以上
に大きく見てしまっているので、自分の対応能力を“極小視”することになるのです。
ですから“ディスカウント”は“歪んだ物事の見方、感じ方、とらえ方”であると言えるのです。
どうしてこんな歪みを身につけてしまうのか?
それは、自分が、傷つけられたり、ぶち壊されてしまうような不安や脅威にさらされると、私達
は、自分の身を守る対応行動をとります。そこで、自己防衛のために“何とか、危険を見たり、感じ
たりしないですませる”ために、身を丸めて小さくなったり、逃げたり、こまかしたり、相手を攻撃
・排除しようとしたり、あたかも何も感じていないかのような振りをしたりするのです。
こうして、自己防衛のために、“歪んだ物事の見方、感じ方、とらえ方、反応の仕方、行動の仕方”
を身につけてしまうのです。
二つの方向のエネルギーの流れ
ディスカウントのメカニズムをよく考察してみると、そのエネルギーの流れる方向は2つあります。
一つの方向は、その人自身の内側に向かつて流れるものです。内側に向かって流れるエネルギーは、
“自分自身へのディスカウント”になり、自分の能力や可能性、実際の行為の意味合いや価値を
ディスカウントするようになります。
もう一つのエネルギーの流れの方向は、自分の外側へ向かって流れるものです。これは、自分の
周囲にある、“ 相手の人や周囲の状況へのディスカウント”になります。
基本的な4つの問題のある行動のパターン
多くのディスカウントの事例を、エネルギーの流れと関連つけて考察した結果、自己防衛のために
身につける問題のある行動(ディスカウント行動)のパターンは、基本的に、次のような4つの
ものにまとめられます。そして、それらが複合し合って、更にいろいろなものを形成していると考え
られます。
① 萎縮・閉じこもり・自己否定・無力化
② 抑圧・感じない体制(感覚鈍麻)
③ 対抗・攻撃・爆発
④ 逃避(逃げる・避ける)・誤魔化す・はぐらかす
これらは次のような図にまとめることが出来ます。
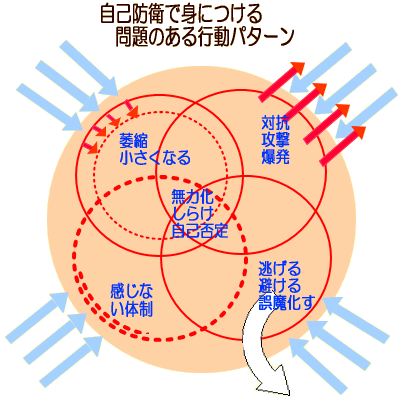
ストロークとディスカウントについての余話
1.ストローク・ディスカウント理論の構築は、シフ派のおかげ
一つの心理療法の理論が、妥当性があり、有効であると判断されるのは、精神病の中でもっとも
治療が難しい統合失調症(分裂病)を、その理論と方法論で治療できるかどうかで判断されます。
『TAは有効な心理療法の理論である。』と評価されるようになったのは、TAの理論的枠組みで
統合失調症(分裂病)の治療に当たり、大いに成果を上げた、ジャッキー・シフ博士の功績と言わ
れています。
2.再養育派と再決断派の勢力争い
シフ博士と、その周辺に集まる人達を、シフ派、あるいは“再養育派”と呼びます。それは、そ
の治療方法が、患者を、まさに赤子の様な状態にまで退行させて、そこから健全なストロークを与え、
愛されているという実感を与え、ストロークの授受の体制を形成し直し、人柄の再構築を計る方法
を用いたことから“再養育派”と呼ばれるようになったのです。
再養育派は、TAの中に、ストローク、ディスカウントの概念を持ち込み、TAの基本的理論の構築
に寄与したのです。さらに、統合失調症の患者さんの行動とその変容の観察の結果から、ストローク
とディスカウントのいろいろな理論を積み上げていったのです。
ところが、再養育派は、ある治療で事故を起こし、グールディング夫妻を中心とする“再決断派”
のメンバー達に、その責任を問われ、国際TA協会を退会せざるを得なくなる出来事がありました。
TAを学ぶ最高レベルにある人達も、こうした“権力争いのゲーム”をしていることを見ると、
頭で考えることを、行動で実現することは、非常に難しいことであるのがよくわかります。
3.ディスカウントされる“ディスカウント理論”
残念なことに、それ以後、国際TA協会の中では、ディスカウントの理論は何らの研究も進まず、未
整理のまま現在に至っているのです。このために、現在でも、ディスカウントの理論は統合性(まと
まり)がなく、いろいろな研究者が掲げる各項目は、ばらばらで、筋の通った説明をしようとすると、
自分なりのいくつかの試論で補わざるを得ないのです。
私は、精神分析の“防衛機制のメカニズム”の理論に立って、ディスカウント理論を考察して、
統合性を持つように構築してみました。
こうして出来上がったものが、上図の“自己防衛で身につける問題のある行動パターン”です。

