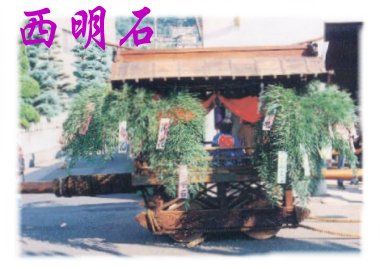◆だんじりの姿
唐破風は左右にゆるやかに下る。鬼板は前後部ともに鬼。頭上に鳥衾が長く出る。破風下の懸魚は、前後部とも鷹と老いた松が彫られており、どちらがだんじりの前か後ろか判別が難しい。軒の下に15本の疎垂木、その先には左三つ巴文と「丸に二」文を交互にはめ込んでいる。1本の柱の木鼻も2つの唐獅子の阿・吽を飾る。計8個。
囃子座の四隅に錺金具のついた擬宝珠高欄を立てる。台座の4面に各々3個の金具を張り付けている。台座の幕板をはめ込む部分には、2間に分割し格子2本を対角線に向けて斜めに組んだものとなっている。◆だんじりの歴史
町内の古老によると、西明石のだんじりは昭和3年ごろに製作された。ケヤキ製。
工事にあたっては、当時の当町内の長老数名が羽織り袴姿で、奥町内まで出掛けた。だんじりの拝見を願い出て、それを参考に建造したと伝えられている。なお、だんじりの図面・材料・技術の指導は京都の宮大工に依頼したいという。