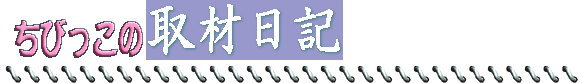
吉備路探検隊 2000.5.11.thu
倉敷市立倉敷西小学校の6年生がウォークラリーを行いました。
グループに分かれて地図を見ながらチェックポイントを回るというものです。
チェックポイントは造山古墳・備中国分尼寺跡・こうもり塚古墳などで、
それぞれのチェックポイントではクイズが出題されています。
社会科ではじめて歴史の勉強をはじめる小学6年生が
歴史の興味を持つようにと
実際に古墳などを見て勉強するというのが最近は多いそうです。
わたしが小学生だった頃はこんな勉強あったかな?
歴史に興味はあるんだけど・・・
ちょっと思い出せません。
 ですから、「こんなに歴史や文化が豊かに感じられる環境(吉備路)で学べるのって良いな」
ですから、「こんなに歴史や文化が豊かに感じられる環境(吉備路)で学べるのって良いな」
と、子供たちをうらやましく思いましたけれども、
子供たちに感想を聞くと、そんなことちっとも幸運に思っている節は無くて
「こうもり塚古墳にこうもりが本当にいた」とか
「きりぎりすがいた」とか言ってるんです。
(確かに草花はぐんぐん伸びてるし生物がたくさんいて力強い自然の成長を感じる良い季節なのだけれども)
子供っていろんなところに興味を持ちますね。
でも、ひょっとしたら私も小学生の頃、
せっかく歴史的にスゴイ史跡に行っているのに
「花咲いてる」とか「虫がいる」とか言っていた子供だったかもしれないな、と思いました。
だから小学生の時の歴史の勉強について思い出せないのかも。
でも、こういう実地研修のような学習は「そこで何を覚えるか」ではなくて
「そこで何を感じるか」が重要なのであって、
それが「興味を育てる」ということなのかもしれません。
だから古墳を見学しているにもかかわらず古墳のそばに住む小さな生物に気を取られても
かまわないのだなと思いました。
それで、昔の建造物に親しみをもてていたら、意識が完全に「歴史」に向き合っていなくても大丈夫なんだと思います。
 今日の発見
今日の発見
・いつも「備中国分寺」を呼んでいるものが実は「備中国分寺跡」だったこと。
今あるのは江戸時代にたてなおされた「日照国分寺」だった。
・こうもり塚古墳の名前の由来は「石室にこうもりが住んでいるから」だった。
こうもり塚古墳…6世紀後半に築かれた前方後円墳。
仁徳天皇の恋物語に出てくる黒姫の墓とも言われている。
・たくさんのかえるが芝生ではねているのを見た。
その直後、雨が振り出した。かえるは雨を予知するって本当なのかも。
Friday, May 12, 2000 0:18:11
化学消防艇「みずしま」 2000.5.12fri
本荘保育園(倉敷市)に通う子供たちは、4歳になると「幼年消防クラブ」に入会します。
今日はその発会式が臨港消防署で行われました。
子供たちは発会式のあと、救急車やタンク車、ポンプ車、化学消防車などの消防車両を見学しました。
私もデジカムで撮影しながら運転席に上ったりしました。
車内にはいろんな装備が備え付けられていて、
緊急時に役立つ機械がたくさん搭載されているんだと思いました。
(モニターのようなものとか無線とか背負うボンベ状のものとか…うまく言えないけれど)
臨港消防署は、県内最大の工業地帯「水島コンビナート」での火災に対応すべく設けられた特殊な(?)消防署です。
ここが出動するときというのは、とても「怖い」火災が起こったときなんだと思います。
水をかけてはいけない火災の時に出動する化学消防車もあります。
水をかけても消えない火災ってどんな火災なんだろう?極めて高温の火災なのかな。
また、管内に重要港湾である水島港があり、離島も多い臨港消防署は、
岡山県内で唯一「消防艇」を所有する消防署でもあります。
化学消防艇「みずしま」は、海の上での消防と救急の両方の役割を担っている消防艇です。
機関銃のような大砲のような「放水砲」というものが5砲あります。
いろいろな災害のケースに対応できるように準備されていて
消防署の方が頼もしく思えました。(そういう技術も日進月歩なのかもしれませんが)
子供たちは消防署がどんな仕事をして自分たちを守っているのかがわかったんじゃないかな。
私はこっそり、署員さんたちが眠る部屋も見せてもらいました。
消防署の仕事は24時間交代で、出勤と休日が1日づつと聞きますが
すごく大変な仕事だろうなと、コドモのように感心してしまいました。
幼年消防クラブは、幼い頃から防火意識を育てようと昭和60年から始まった運動で
現在倉敷市内には15クラブ・1000人のクラブ員がいるそうです。
今日の発見
・消防自動車の横に付いてるホース(黒くって1周くらい巻いてるやつ)は、そこから水が出て消火するためのものではなくて、池とかから取水するためのものだった。少し想像力を働かせればわかることでしたが…
・水島港にくらげがたくさんいた。カラーゼリーではないようだ…
Saturday, May 13, 2000 13:52:56
古代吉備王国の幻の酒 2000.5.13.sat.
鬼ノ城たたら倶楽部という総社市の市民グループは
「おにと鉄」をテーマに鬼の城のふもと(総社市の西阿曽とか奥坂とか)で活動しています。
二年前から大正時代に栽培されていたという酒米「都」の種もみ作りをはじめ、
去年は80年ぶりに復活した「都」を使って酒「鬼鉄」を作りました。
 手作りで復活させた幻の酒米「都」がこの度山手村に提供されることになりました。
手作りで復活させた幻の酒米「都」がこの度山手村に提供されることになりました。
はじめは幻の酒米の門外不出を決めていた鬼ノ城たたら倶楽部でしたが
山手村からの「永続的に村おこしとして都を栽培していきたい」との強い要望と
酒造りの時に協力を得ている三宅酒造(山手村宿)からの口添えもあり、貴重な酒米の寄贈が決まりました。
総社市と山手村の友好を深める意味での提供でもあり
贈呈式は総社市長の立会いの元に行われました。
山手村では山手農業公社が合鴨農法でこの「都」を育て
栽培には山手村内の小中学生も参加するそうです。
田植えは6月中旬に予定しています。
古代山城「鬼の城」の発掘の進む総社市には、鬼伝説「温羅伝説(うらでんせつ)」が伝わっています。
酒も米も古代吉備王国の技術を学びながら復活させている鬼ノ城たたら倶楽部は
なんと、鉄も作っています。鉄を作るための炭も手作りで作っています。
鉄造りは、地元総社市立阿曽小学校4年生の「総合学習の時間」に取り上げられる予定です。
また今日は、岡山県教育委員会から10月に行われる「ふるさと発見イベント」に、
鬼ノ城と、その伝説を守ろうとしている人々を取り上げたいと要請もありました。
10月の3日間、鉄を作ったり地元の祭りに参加したり鬼ノ城に登ったりして体験するイベントです。
面白そうなイベントです。
 実際、最近の鬼ノ城の発掘調査の結果、なんと、たたら跡(製鉄所跡)が見つかっているのです。
実際、最近の鬼ノ城の発掘調査の結果、なんと、たたら跡(製鉄所跡)が見つかっているのです。
古代山城にたたら跡が見つかったのは日本ではじめてのことです。
鬼ノ城が何らかの形で「自給自足」していたことを示す事実です。
歴史的事実を受けて意気あがる鬼ノ城たたら倶楽部の皆さん。
「鬼ノ城たたら倶楽部」は今年注目です。
今日の発見
・古代吉備王国の幻の酒「鬼鉄」は、甘口でたいへん飲みやすいお酒です。
Monday, May 15, 2000 0:34:37 鬼の城(写真提供きむきむさんです)
船穂町60周年・町立図書館落成 2000.5.14.sun.
船穂町が町政施行されたのが昭和15年。今から60年前のことです。
今日は船穂町の町政施行60周年記念式典が行われました。
今や2300世帯・7800人が住む船穂町は、
マスカットやピオーネ、スイートピーという特産品で有名な町です。
近隣市町村の首長や議員などが多数出席した記念式典では
教育とか福祉とか地方自治とかの部門で長年功労のあった人に表彰状が贈られました。
こういう式典では「挨拶」が多くて、今日の式典でも例に漏れず、なんと10人以上の人がステージの上でお祝いの言葉を話しましたが、
ステージの上で発せられた言葉のなかでいちばん印象に残っているのが
受賞者を代表してお礼の言葉を話した浅野さん(JA倉敷西組合長)の言葉です。
内容は「21世紀の船穂町の発展のためにこれからも努力していきたい」というものでしたが
たくさんの来賓と町民が見守るなかの表彰は、きっと感動的であったろうと思います。
その言葉からは感激と緊張が伝わってくるようでした。
船穂町では60周年記念事業として町立図書館を建設しました。
町民会館の隣に、小川が流れ水車が回る中央公園が新しく作られ、
図書館はその中央公園の中にあります。
図書館の外観は船穂町のシンボル「高瀬通し」をイメージして
なんとなく船を感じさせるデザイン。
船穂町民図書館では、読書はもちろんインターネットを無料で利用できます。
今日の発見
図書館の前の中央公園にはブロンズ像「日ざし」が設置されました。
帽子をかぶった女性の像ですが、この像を見るのに1番良い時間は3時ごろだそうです。
「日ざし」の文字通り、日ざしを受けている(顔が太陽のほうを向いている)からだそうです。
朝見たら後光がさしているように見えました。
・船穂町では最近フルーツフラワーセンターにマスカットの直売所を設けました。
今は出始めなのでどこに行っても高いですが、マスカットやピオーネを買うならここで買うのが安いし新鮮でいいです。お店のおばちゃんは4チャンネルを良く見てくれているようです。
温室で栽培しているので「旬」というものは無いそうですが、路地ものなら6月から7月頃が良いそうで
その頃が1番出回り値段も手ごろになるのでは、と思われます。
Monday, May 15, 2000 1:17:46
「緑を大切に」ふれあい保育 2000.5.15.mon.
酒津公園の花壇は、倉敷市内の福祉施設「ひまわりの園」が委託を受けて世話をしています。
花壇の花は春・夏・冬と季節ごとに植えかえられています。
その春の植え替え作業をおととしから倉敷市内の保育園の子供たちが手伝っています。
子供たちの「育てる」心を養おう・地域の美化活動に参加してみよう・花壇の世話をする仕事について知ろう、とのぞみ保育園が中心に進めている活動です。
(園長の小松原勇さんが緑とのふれあいなどにとても熱心な方なのです)
111人の園児たちはロベリアという花を約1000株植えました。
酒津公園の東側の入り口すぐの所です。
 今日の発見
今日の発見
ロベリアという花について。
ロベリアはキキョウ科の植物でこんもりといた株に小さな花をたくさん咲かせます。
ブルーが主流のようです。
花の形が小さな蝶々のようにも見えることから和名は「ルリチョウチョウ」というようです。
花の時期は5月から7月頃ですが、花の期間が長く一ヶ月以上咲くとのことです。
珍しい花ではナイですがパンジーやペチュニアほど出回っているわけではないので
花壇からこっそり盗っていくひとがくることが予想されるそうです。
ほかの花のときでも一晩に15株くらいとられたことがあるとか…
みんなの憩いの場をきれいにしようといている子供たち。
その花を盗んだりごみをすてたりする大人。
子供たちの「公園を愛する心」を育てるためにも
(子供たちが「心無い大人」に成長しないためにも)
大人はマナーを守らなくてはいけません。本当に。
夏に向けて「プールの掃除」 2000.5.16.tue.
なんと、夏に向けてプールの掃除を行った小学校があります。
高梁川の西、総社西小学校です。
一年間放置されていたプールの底にはびっくりするほど泥と枯れ葉がたまり
壁面には藻のようなものがこびりついています。
汚れはたわしを使ってもなかなか取れませんでした。
子供たちはたわしのカネの部分を使って汚れをこそぎ落としていました。
(塗料も一緒に…)
塩素を使わなくなったことから藻も多く発生するようになったようです。
この小学校の校長先生は土岐先生という女の先生で感じのいい方でした。
総社西小学校は総合学習の時間に「高梁川・神在川?・落合川?」と、川が近くに多いことから
環境学習をするそうです。
総社市の川西地区で唯一障害者学級があるため、
ボランティアに関する学習にも取り組むそうです。
また、この小学校にはコンピューター教育のレポートで去年賞を受賞した先生がいらっしゃるとかで
なんと栃木県のある小学校とテレビ交換授業をする予定もあるらしいです。興味深いです。(6月6日に実施)
真備ふれあいの家 2000.5.17.wed.
真備町箭田にある精神障害者の通所共同作業所です。
真備町に委託を受けて「家族の会」が平成9年から管理運営しています。
活動をはじめて4年目なのでまだまだ試行錯誤しながらの運営のようですが
今当惑していることがあるそうです。
それは、最近ニュースなどでよく聞く「精神鑑定」という言葉についてです。
最近低年齢の犯罪が増えてきて、責任能力があるないかの「精神鑑定」を実施するというのをよく聞きます。
精神鑑定で、精神に問題があると判断されれば、犯罪にならないこともありえるわけで、
容疑者の精神鑑定結果は注目されるところです。
しかし
真備ふれあいの家では、「精神鑑定」という言葉を聞くたびに
「精神障害者は何をするか分からない」「精神障害者には善悪の判断はつかない」と、精神障害者は危険だと言われている気がして肩身の狭さを感じているそうです。
ふれあいの家の共同作業所に通っている方は心に病を抱えながらもまじめに働いているかたがたなので、
心を痛めているそうです。
犯罪を犯す人のホトンドは責任能力のある人たちだし(だと思うし)、
人と人との関係のみならず動物同士(人間含む)のコミュニケーションは
信頼関係だなと思うのです。
ふるさと探訪 2000.5.19.fri.
総社市の小学校は4年生の社会科の授業で「ふるさと総社探訪」として、
総社市内の史跡や施設を見学する校外学習を行います。
総社市立総社東小学校の「ふるさと総社探訪」を取材しました。
総社下水処理場
総社の市街地からでる下水を処理している施設です。
下水は「沈殿させたり、微生物に処理してもらったり」してきれいになります。
施設内は思ったよりにおいませんでしたが、やっぱり匂いました。
アンモニアっぽいにおいでした。
処理されている途中の下水はにごっていて泡立っていて、
ほんとにこんな水がきれいになるのかなと思うくらいでした。
下水処理施設というのは町より低くて川に近いところに建設するそうで、
総社下水処理施設も高梁川に近い総社南高校の東側にあります。
吉備路クリーンセンター
真備町箭田にあるごみ焼却処理場です。
総社市・真備町・清音村・山手村の1市1町2村からのごみを処理します。
平成9年に建設されたばかりの最新鋭の技術が駆使された施設です。
高温の砂を攪拌することでごみを完全に燃やすことのできるごみ焼却処理施設と
不燃物の中から鉄やアルミをリサイクルのために回収できる不燃ごみ処理施設が併設しています。
(磁石で鉄やアルミを別々に集めるのです)
すべて、オートメーション化されていて、
なんだか大きなマジックハンドのようなものでごみがあっちに行ったりこっちに行ったり。
最近ごみは分別収集していますが、ごみ処理場では、さらに分別されて、
素材ごとに業者が買い取っているそうです。
そして、この施設の特徴はケムリを処理して公害防止にもつとめているそうです。
匂いはしませんでした。(近くの竹炭窯が竹を焼いている匂いはしましたが)
施設はきれいだったし、見学者用のルートもあって、なんだか新しい施設でした。
宝福寺
画聖雪舟が幼少の頃修行したことで知られる臨済宗のお寺。
涙で書いたねすみの話は有名です。
重要文化財の三重の塔があります。
ここでは雨が降ってきてしまって残念。
お弁当を食べました。
総社東小学校の4年生は完全に女の子が男の子を尻に敷いています。
男の子曰く「女子の頭には角があるんだよ−」ですって。
その他、消防署にも行きました。
ふるさと探訪のねらいは
古い文化を大切にする心を育て
現在の生活を支えている公共の仕事の大切さを学ぶことだそうです。
児島武道館30年記念柔道大会 2000.5.21.sun.
 児島武道館は倉敷市が児島・玉島・旧倉敷に合併してから最初に作られた武道館で、今年で30年になります。
児島武道館は倉敷市が児島・玉島・旧倉敷に合併してから最初に作られた武道館で、今年で30年になります。
ここは毎年5月に、創立を祝って近隣のスポーツ少年団や武道館などを招き創立記念柔道大会を行っています。
今は児島地区の小中学生20数名が「児島柔道スポーツ少年団」として児島武道館で稽古をしています。
いまは、サッカーや野球などの人気に押されて柔道人口が減りつつあるようですが、
柔道は、勝ち負けではなく「教育的価値の高いスポーツ」なんだそうです。(大会委員長談)
たとえ劣勢でも最後まであきらめず、価値を望む心を育て、自分の心で勝つことを覚えるのだそうです。
(今回はじめてちびっこがデジカメでの撮影を行いました。映っているのはカメラマンのKさんです)
 今日の驚き
今日の驚き
岡山県はかつて柔道先進県で、
特に女子柔道に関しては、今も全日本女子柔道大会は岡山で開かれるほど先進的な県だったそうです。
(6月に開催されます)
児島武道館もかつてはオリンピック選手を輩出したこともあるそうです。
交通死亡事故多発警報 発令中! 2000.5.23.tue.
倉敷地方では、交通死亡事故が増えています。
5月14日から20日までの間に5人も死者が出ています。
そこで、倉敷地方と井笠地方を合わせた「倉敷ブロック」では
「交通死亡事故多発倉敷ブロック警報」が発令されました。
これは10日間の間に5人の交通事故死亡者が発生した時に出される警報だそうです。
倉敷ブロックの場合7日間で5人(昨日も一人亡くなったし)も亡くなっているので
立て続けに不幸な事故が起こっていることになります。
5件の死亡事故のうち、二人は総社市の人です。
一人は90歳の老人で、自宅の前の道路(180号線)で、自動車にはねられたそうです。
もう一人は16歳の少年です。
バイクに二人乗りしていて自動車とぶつかりました。
かなり無茶な運転をしていたようです。
今日は、総社市の交通安全母の会の取材に行ってきたんですが
(総社市内の小中学校のに通う子供の母親で構成される団体です)
死者の一人が16歳と、子供の年齢にも近いことから、この事態を重く見、
「各学校でもこの事実を周知させよう」「チラシを配って呼びかけよう」ということを、計画していました。
25日に総社市日羽の国道180号線で、街頭啓発をするそうです。
交通死亡事故は加害者も被害者も悲しい思いをします。
防げるものなら防ぐべきだと思います。
交通マナーやルールを守らない未成年は、母の愛を知って改心してほしいなあと思いました。
高瀬舟の歴史 2000.5.25.thu.
高瀬舟は河川を使って人や物を運ぶ川舟で、高梁川でも昭和初期まで運行されていました。
近代的な交通移動手段が確立されるまで、高瀬舟は、流域の文化発展生活向上に寄与してきました。
船穂町にはパナマ運河より200年以上古くから建設されていた閘門式運河「高瀬通し」があることでも有名です。
また、高梁川の高瀬舟は正倉院の記録に残っており、少なくとも奈良時代からかたちはどうあれ運行されていたようです。とても歴史があるのですね。
昭和初期に高梁からの最後の高瀬舟で船頭をつとめた人に「小見山元治」さんという方がいらっしゃって
高瀬舟から降りたあとも、高瀬舟を愛し、高瀬舟の保存のために力を尽くされたそうです。
現在、高梁市の観光駐車場に高瀬舟が設置されているのはこの小宮山さんの呼びかけの力によるところも多いとか。
そもそも小宮山さんは、備中松山城の殿様を乗せる高瀬舟を代々運行する家の生まれだそうです。
今は小宮山さんはおなくなりになっていて、娘の野田和心(かずみ)さんがその遺志を継ぎ、高瀬舟の研究を続けています。
今日の取材では、野田和心さんのお話を聞いたのでした。とても勉強になりました。
高瀬舟についてはこちらに詳しいページがあります。
万寿の子炊爨〜ますのこすいさん〜 2000.5.26.fri.
 酒津公園で倉敷市立万寿小学校の全校児童が
酒津公園で倉敷市立万寿小学校の全校児童が
1年生は6年生・2年生は5年生・3年生は4年生の兄弟学級でグループを作り
飯盒炊さんに挑戦しました。
お米だけを炊いておかずは家から持ってきています。
学校のねらいは学年間の交流です。
火を使う飯盒炊爨で、上級生の責任感を育てます。
また、「同じ飯盒の飯」を、食べた子供たちは、
「去年より早くできた」「うまく火をつけることができた」
「今まで食べたなかで1番おいしいご飯」などと感想を口にしながら
自分がたいたホカホカのご飯を食べていて、
わたしは、子供たちの純粋な成長に感心してしまいました。
 万寿小学校の子供たちは、毎年この飯盒炊爨で成長するようで
万寿小学校の子供たちは、毎年この飯盒炊爨で成長するようで
特に6年生はかまどの火の起こし方や飯盒の取り扱いなど慣れた感じでやっていました。
私は、長い間、ボーイスカウトのリーダーをしていたもので
飯盒で米を炊くのには自信があるんです。
思わず口を出したりして…
私もやってみたかったな。
カメラマンはM野さんです。
たまの港フェスティバル 2000.5.27.sat./28.sun.
嵐で始まったたまの港フェスティバル。
初日の27日、晴れたのは13時から14時までの小一時間と深夜だけでした。
たまの港フェスティバルは、船と港をテーマにしたお祭りです。
玉野市宇野港周辺を舞台に開催されます。
イベントは、瀬戸内海クルーズや出店・ステージ・フリーマーケットなど。
海関係のお店もたくさんでます。
でも、初日の27日は雨と強い風のため昼過ぎにイベント中止となってしまいました。
夜のイベント「ありがたやお月様」は屋内で開催されました。
28日は、KCTで生放送を行いました。
放送は、午後1時から午後2時まです。
放送では、広い会場で行われていることを、VTR(フリーマーケット「熱風市場」・子供広場・船上結婚式など)を交えながら紹介します。
初日で撮影しておく予定だったVTR(雨のため中止になった熱風市場など)を、中継当日の朝に撮影することにもなり、アクシデントがないことを祈る中継準備でした。

私は、今回はじめてたまの港フェスティバルにお目見えした「御座船・元禄舟遊び」を中継前に取材しました。
御座船は江戸時代に、西国・九州の諸大名が参勤交代の際にお供の船を引き連れて瀬戸内海を往来したとされる殿様の船です。
天下泰平の世、殿様が出来映えを競ったとされる御座船は豪壮華麗で、いわば諸大名の「自家用豪華客船」として往時の瀬戸内海に華やかな海遊絵巻を繰り広げたそうです。
たまの港フェスティバルに来た御座船は「御座船・備州」といいます。
御座船備州は、岡山藩の池田の殿様の御座船「住吉丸」を倉敷市下津井の下津井祇園神社に残る模型をもとに再現したもので、昭和61年に瀬戸大橋開通を祝う意味で建造された多目的観光船です。
 今回、たまの港フェスティバルではこの御座船に乗って舟遊びする瀬戸内海クルーズ「元禄舟遊び」が、イベントとして行われたのでした。
今回、たまの港フェスティバルではこの御座船に乗って舟遊びする瀬戸内海クルーズ「元禄舟遊び」が、イベントとして行われたのでした。
瀬戸大橋やたくさんの島、玉野の三井造船の造船所とかを、海上から見ることが出来ました。
(カメラマンはH君です)
生放送中の役目はメインステージで披露される「HIPHOPかっからか」を紹介することでした。
かっからかとは玉野市に古くから伝わる地踊りです。
盆踊りがニューバージョンにアレンジされるのは最近の流行のようで
玉野のかっからかも去年からか「ロックバージョン」が作り出されたばかりです。
ロックかっからかを見た若者が、「玉野に活気を」「かっからかのアレンジはいける」と、考案したのが「HIPHOPかっからか」です。
生放送中唯一[生で動いてるもの]を伝えようとちびっこ緊張していましたが、
番組も、ステージも押し気味で?進行し、結局時間切れにおわりました。(悲)
太鼓たたきはじめた頃番組終了。
しかもENG取材したVTR「元禄舟遊び」も時間押しのため放送されず。(涙)
それぞれのペースで進行する番組とステージを調整するのは難しかったです。
HIPHOPかっからかはというと…
YO−YO・HO−HO言ってました。私はてっきりHIPHOPダンスだと思っていましたが違いました。
HIPHOPの皆さんは頑張っていただきたいです。
ちびっこ仕事消化不良のまま終わってしまった生中継でした。
それにしても、日ざしが強くなっています。中継スタッフはみんな(中継車内に居た方以外?)ひりひりと日焼けしてました。スゴイ紫外線でした。
そろそろ紫外線対策をしなくてはいけません。
5.30ごみゼロの日 2000.5.30.tue.
真備町は5月30日ごみゼロの日にちなみ
30日から一週間を「ごみ減量・リサイクル推進週間」と定め
ごみ減量に関する啓発活動を行います。
初日の今日は町長自らがごみ収集車に乗りこみ
燃えるごみの収集を行いました。
首長が郵便配達ってのは聞いたことがありますが(総社市)
ごみ収集というのはあまり聞きません。
真備町長の鎌田よりやす氏は若くて行動的なので作業服も似合っていました。
ちなみに真備町のごみ減量・リサイクル週間の活動としては新入職員が研修としてごみ収集を体験するほか
シンポジウムや、ごみの不法投棄の実態をパトロールしたりするそうです。
真備町といえば、弥高山の産業廃棄物が問題です。
弥高山に放置された産業廃棄物からは、大変危ない物質が溶け出し小田川が汚染されてしまうということです
また、井原線が開通し開けた土地には、こころない人がごみを捨てていくとのこと。
弁当のごみとか 空き缶とか。
真備町では「水と緑の環境保全の町」を宣言し、
環境美化条例を施行することになりました。
ごみ減量・リサイクル推進週間では、その条例の広報も併せて行うということです。
でも、ごみの不法投棄って、多分、町外の人や業者がいけないことをしてるんじゃないかな。
ごみは「処理する」ことより「減量」することが大切です。
処理できないから不法に捨てるのでしょう。
処理できないのなら造ってはいけません。
大量生産大量消費で景気の良い日本はもう終わったんです。
世界禁煙デー 2000.5.31.wed.
 5月31日は、WHO(世界保健機構)が定めた世界禁煙デーです。
5月31日は、WHO(世界保健機構)が定めた世界禁煙デーです。
31日から一週間は禁煙週間です。
31日はJRの駅前などで禁煙デーのPRが行われました。
倉敷駅でも朝のラッシュ時(7:30頃)から広報活動が行われ
倉敷保健所の職員や管内の愛育委員さんがチラシやティッシュを配りPRしました。
チラシを見て目に付いたのは「子供のうちから煙草を吸うと体に悪いです」などという文です。
そんなに喫煙する子供が多いのだろうか。子供は煙草吸っちゃいけないです、日本では。
その感想を一緒に取材に行ったHくんにいうと、彼曰く
「大人がやめない限り、子供は煙草吸うよ」
ごもっともです。
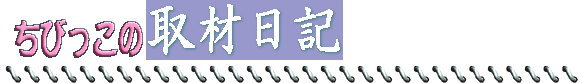
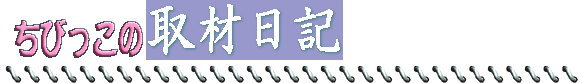
 ですから、「こんなに歴史や文化が豊かに感じられる環境(吉備路)で学べるのって良いな」
ですから、「こんなに歴史や文化が豊かに感じられる環境(吉備路)で学べるのって良いな」 今日の発見
今日の発見 手作りで復活させた幻の酒米「都」がこの度山手村に提供されることになりました。
手作りで復活させた幻の酒米「都」がこの度山手村に提供されることになりました。 実際、最近の鬼ノ城の発掘調査の結果、なんと、たたら跡(製鉄所跡)が見つかっているのです。
実際、最近の鬼ノ城の発掘調査の結果、なんと、たたら跡(製鉄所跡)が見つかっているのです。 今日の発見
今日の発見 児島武道館は倉敷市が児島・玉島・旧倉敷に合併してから最初に作られた武道館で、今年で30年になります。
児島武道館は倉敷市が児島・玉島・旧倉敷に合併してから最初に作られた武道館で、今年で30年になります。 今日の驚き
今日の驚き 酒津公園で倉敷市立万寿小学校の全校児童が
酒津公園で倉敷市立万寿小学校の全校児童が 万寿小学校の子供たちは、毎年この飯盒炊爨で成長するようで
万寿小学校の子供たちは、毎年この飯盒炊爨で成長するようで
 今回、たまの港フェスティバルではこの御座船に乗って舟遊びする瀬戸内海クルーズ「元禄舟遊び」が、イベントとして行われたのでした。
今回、たまの港フェスティバルではこの御座船に乗って舟遊びする瀬戸内海クルーズ「元禄舟遊び」が、イベントとして行われたのでした。 5月31日は、WHO(世界保健機構)が定めた世界禁煙デーです。
5月31日は、WHO(世界保健機構)が定めた世界禁煙デーです。